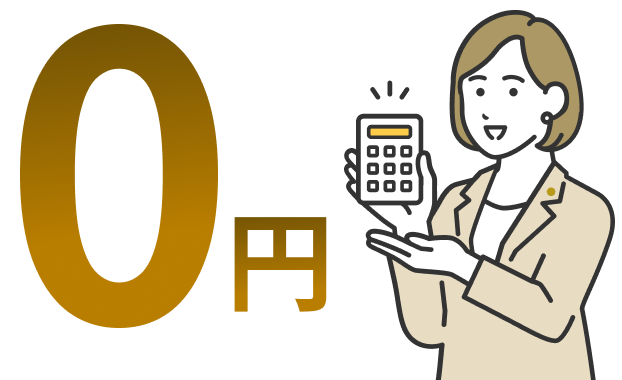認知症でも遺言能力は認められる? 遺言能力をめぐるトラブルの対処法
- 遺言
- 遺言能力

高齢化が進展する近年では、誰しもが認知症の当事者、または支えるご家族になる可能性があると言えます。仙台市では、「認知症ケアパス」という小冊子を作成し、市内の地域包括支援センターなどで配布する取り組みをしています。このような取り組みは、ご本人やご家族などが抱える不安や負担を軽減し、適切な対応を知るきっかけとなることでしょう。
相続の場面においても、認知症の方が遺言書を作成するときには、後日遺言能力の有無をめぐってトラブルになることがあるため、適切な対応を知っておくことは大切です。
本コラムでは、「遺言能力」について解説し、遺言能力をめぐるトラブルの対処法をベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士がご説明します。
1、「遺言能力」とは?
形式面で問題のない遺言書が作成されていても、遺言者に「遺言能力」がない状態で作成された遺言書は「無効」になります。
-
(1)遺言能力の有無
遺言能力とは、遺言者が内容を理解し、遺言結果を認識できる意思能力を言います。
遺言書は、遺言者自身の最期の意思を遺産分割に反映させることが目的です。そのため、遺言の内容を理解できない状況で作成した遺言が影響を及ぼしてしまうと、遺言の趣旨に反するため、無効として扱われます。
つまり、認知症などで意思能力を欠いている状況で行われた遺言は、遺言能力を欠いているとして、無効になる可能性があるでしょう。 -
(2)遺言に関する年齢の制約
遺言に関しては、民法961条に次のような規定があります。
民法 第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる
つまり15歳にならないと、有効な遺言をすることができないということです。
15歳未満であれば、遺言書を作成しても無効になります。親などの法定代理人が、本人を代理して有効な遺言書を作成することもできません。 -
(3)認知症と意思能力
15歳以上であれば有効に遺言をすることができますが、「意思能力」は必要です。
そのため、遺言者に認知症の疑いがあるときは、遺言時に「意思能力があったかどうか」が問題になります。ただし、認知症と診断されたとしても、すべてのケースで「意思能力がない」として遺言能力が否定されるわけではありません。
たとえば、認知症がすすみ、判断能力が欠けているのが通常の状態になっている場合は、家庭裁判所で後見開始の審判をすることができます。審判を受けることにより、財産に関する法律行為を本人に代わって行うことができる成年後見人が裁判所によって選任されることがあります。
審判を受けた人を「成年被後見人」と言い、「成年被後見人」の遺言については、民法で次のような規定が設けられています。民法 第973条1項
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
判断力が欠けている状態が常である「成年被後見人」は、基本的に意思能力を有しないとされます。しかし一時的に回復したときには、「医師2人以上の立ち会い」という条件のもとで有効に遺言ができるとするものです。
なお、被相続人が、「成年被保佐人」や「成年被補助人」であるときは、医師の2人以上の立ち会いがなくても有効に遺言できます。
したがって認知症であっても、成年被後見人に該当しない場合は、条件なく単独で遺言を有効に成立させられる可能性があります。ただし相続人や受遺者などが、遺言時の「意思能力の有無」をめぐって遺言の有効・無効を争ってくる可能性はあるでしょう。
2、遺言能力の判断で考慮されることとは
遺言能力の有無が問題となったときには、最終的には訴訟を提起して判決による解決を図ることになります。
過去の裁判例では意思能力の有無だけではなく、
「遺言書が作成された経緯」
「遺言への不当な干渉の有無」
「遺言の具体的な内容(内容の複雑さや重大性、高額な遺産であるか)」
などの相関性も重要とされる傾向があります。
これらの要素などを総合的に勘案し、遺言能力の有無が判断されると言えるでしょう。
3、遺言能力の有無に関する裁判例
前述したように、遺言能力の有無は一概に判断できるものではなく、それぞれのケースが抱える事情によって判断されるものです。
そのため具体的な事情を弁護士などに相談して、判断の見込みを得ることがおすすめです。
参考までに、遺言能力の有無が問題となった過去の裁判例について、結論とともにご紹介しておきます。
-
(1)高度に認知症が進行していても遺言能力を認めた裁判例
認知症が進行していても、遺言能力があると判断されることもあります。
平成13年10月10日、京都地方裁判所において、高度に認知症が進行している被相続人に対して「遺言能力があったこと」を認める判決が出されました。
原告は、認知症の程度を表す「長谷川式簡易知能評価スケール」の検査結果が4点(高度に認知症が進行していることを表す数値)であることなどから、遺言能力がなかったと主張しました。しかし裁判所は、被相続人の認知症は相当高度に進行していたものの、他者とのコミュニケーション能力や自己の状況を把握する能力を相当程度保持していたと判断しました。
また遺言が作成された経緯や動機に短慮の形跡が見られないことや、遺言の内容が比較的単純で公証人に示した意思も明確であったなどといった事情が総合的に勘案され、遺言能力は認められるとして、原告の請求を棄却する判決が出されています。 -
(2)公正証書遺言であっても遺言能力を認めなかった裁判例
自筆証書遺言に比べて、公証人が関与する公正証書遺言では無効になるケースは少ないと言えます。しかし公正証書遺言の方式で作成されていても、遺言能力はなく無効であると判示した裁判例もあります。
平成14年12月11日に名古屋高等裁判所では、主治医の判断を覆し、被相続人がアルツハイマー型の認知症であったと考えられることなどから、遺言当時、遺言能力はなかったとし、遺言を無効とした控訴人の訴えが認められています。
このケースでは、被相続人は老人性の不可逆的な認知症の症状がゆっくりと進行しており、遺言当時も人物誤認や見当識障害があったことなどから、遺言能力があったとは認められないと判断されました。
4、遺言能力をめぐるトラブルの対処法
遺言能力の有無をめぐって、相続開始後にトラブルにならないようにするためには、遺言当時に遺言能力があることを証明できるだけの材料をそろえておく必要があります。
またトラブルが生じてしまったときには、早期から弁護士に相談することがおすすめです。
-
(1)遺言能力があることを証明できる証拠をそろえる
遺言能力の有無がトラブルにならないようにするためには、遺言当時、遺言者の遺言能力があったことを示す証拠をそろえておくことが有益です。
なぜなら、当事者間の話し合いで解決ができなければ、「遺言無効確認訴訟」の判決で解決するため、「証拠の存在」が判決に非常に大きな役割を果たすためです。
遺言能力を証明するための証拠になりうるものとしては、次のようなものが挙げられるでしょう。- 遺言書作成前後の遺言者の言動や行動などを記したメモ
- 遺言書作成日前後の医師の診断書やカルテ
- 遺言書を作成した経緯や動機が記された書面
- 遺言書を作成するときの様子を撮影した動画 など
-
(2)生前から相続人と話し合いを重ねておく
前述した裁判例にもあるように、医師の診断があっても、公正証書遺言で作成されていても、「遺言能力がない」と判断されることもあります。
遺言者が生前から相続人と話し合いを重ねて、遺言内容への理解を得ておき、相続人同士でも話し合いをしておくことよいでしょう。 -
(3)遺言書の作成やトラブルは弁護士に相談する
遺言能力の有無に関するトラブルを未然に防ぎ、起きてしまったトラブルを事後的に解決するためには、弁護士に相談する方法があります。
遺言を作成する前の段階であれば、弁護士は後に遺言能力が認められる可能性があるのかという判断にくわえ、遺言方式などに関してもアドバイスできるので、有効な遺言書を作成することが可能になります。
また、相続が開始した後に遺言能力の有無が問題となり、相続人などでトラブルになった場合においては、弁護士は事実関係を確認した上で助言を行いつつ、ご相談者の方の代理人として他の相続人と話し合いを進めることができます。
当事者同士だけで話し合いが進まないときでも、弁護士が関与することで、早期に解決できることも少なくないでしょう。
5、まとめ
本コラムでは、遺言能力をめぐるトラブルの対処法について、解説しました。
遺言能力は、15歳以上の意思能力を有する方にあるとされています。
しかし、被相続人に認知症の疑いがある場合などは、遺言能力の有無をめぐって相続人や受遺者が争いになる可能性があるため注意が必要です。
相続にまつわるトラブルが発生してしまったときは、早い段階で弁護士へ相談し、解決を図ることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、弁護士がご相談者の方のお話をしっかりとうかがいながら、解決まで全力でサポートします。
ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています