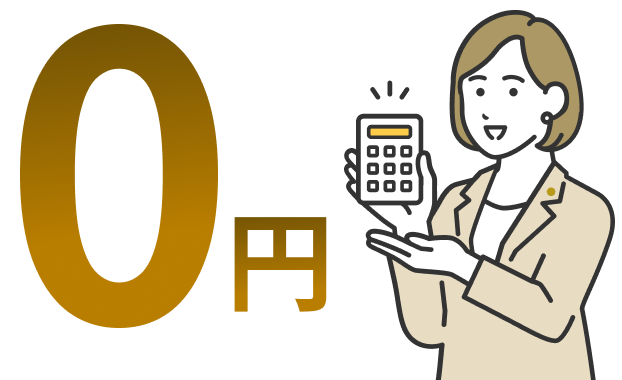遺留分をめぐり兄弟間でトラブルに! 相続における遺留分の考え方
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 兄弟

仙台市が公表している人口動態のデータによると、令和2年10月中に市内で亡くなった方は764人だったそうです。
親族が亡くなった場合、避けて通れないのが相続の問題です。中には、被相続人(故人)が財産の多くを、一部の相続人のみに残していたり、生前に贈与していたりするケースもあるでしょう。このようなケースでは「遺留分」の問題が生じ、相続人間でトラブルになるケースも少なくありません。
そこで本コラムでは、遺留分とは何か? という基本的な知識から、兄弟姉妹など身内と遺留分によってトラブルになってしまった時の対処方法について、ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの弁護士が解説します。
1、遺留分の基礎知識
-
(1)遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺贈・贈与等)に対して制限が加えられている持分的利益のことです。端的に言えば、一定の相続人に最低限保証されている遺産の取り分のことを言います。
遺留分の制度が設けられている背景のひとつは、被相続人の遺族の生活を保障することにあります。
たとえば、被相続人の財産や収入を頼りにして生活する家族がいるのにもかかわらず、被相続人が遺言で「すべての遺産を愛人に譲る」などと指定していたとします。これが実現した場合、残された家族は金銭的に困ってしまうことが考えられます。このような事態を防ぐために、民法では遺留分の制度を設け、被相続人の遺族が最低限相続することのできる遺産の取り分を保証し、ひいては遺族の生活の保障を目指しているのです。 -
(2)遺留分割合の計算方法
遺留分の割合は、民法第1042条において以下のように定義されています。
●直系尊属のみが相続人である場合
3分の1(同条1項1号)
●1号に掲げる場合以外の場合
2分の1(同条1項2号)
3分の1や2分の1という割合が出てきますが、これは「遺留分を算定するための財産の価額」に対する割合であり、これについては後述します。
父Aと母B、その間に子どものCおよびDがいる4人家族を考えてみましょう。
父Aが亡くなり、その遺産の価額(「遺留分を算定するための財産の価額」のこと。)が1000万円だったことが判明しました。
この場合、相続人は、配偶者Bとその子どもCおよびDの3人です(民法890条、887条1項)。そして、B、CおよびDはいずれも直系尊属ではありませんから、今回の具体例は民法1042条1項2号のケースに該当します。その場合の遺留分の割合は、2分の1です。
すなわち、B、CおよびDの遺留分は、1000万円×2分の1=500万円となります(B、CおよびDの総体的な遺留分)。
次に、B、CおよびDの個別の遺留分についてはどうでしょうか。この場合は、法定相続分に従って算定するとされています(同法1042条2項)。
つまり、Bの遺留分=500万円(総体的遺留分)×法定相続分2分の1=250万円
Cの遺留分=500万円(総体的遺留分)×法定相続分2分の1×2分の1=125万円
Dの遺留分=上のCの遺留分と同じ
が個別的な遺留分となります。
なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分権利者には該当しないため注意が必要です。 -
(3)遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる遺産は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」です。
ただし、一部の例外があります。たとえば、被相続人が契約者および被保険者、相続人を受取人とする生命保険の死亡保険金は、原則として「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に含まれません。なぜなら、生命保険金の死亡保険金は受取人の固有財産とされているので、相続財産と扱われないためです。
2、遺留分でもめるケース
-
(1)遺留分を侵害する遺言
特定の相続人に財産をすべて相続させるなど、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言があったとしても、直ちに無効になるわけではありません。前述したとおり、遺留分は被相続人の法定相続人に認められた権利です。遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行う権利を有します。遺留分侵害額請求の進め方は、次の章で解説します。
-
(2)贈与による基礎財産の減少
相続開始前の1年間にされた贈与は、遺留分の基礎財産に算入されるのが原則です(民法1044条1項前段)。
先の例で言えば、父Aがその亡くなる6か月前に子どもCに500万円の贈与をした場合、遺留分を算定するAの基礎財産は500万円ではなく、1000万円となります。
なお、上記贈与が特別受益に該当する場合、相続開始前の10年間にされた贈与も基礎財産として算定することができます。この点は後述します。
また、基礎財産に戻すことができる贈与は上記のとおり相続開始前1年間にされたものに限定されるのが原則ですが、贈与当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知ってした贈与はそのような限定なく基礎財産に含まれます(民法1044条1項後段)。 -
(3)特別受益
遺留分について特にトラブルの原因となりやすい論点が、「特別受益」です。
特別受益とは、被相続人の生前に特定の相続人が受けた、住宅購入資金や生活資金の援助など、他の相続人と比較した場合に明らかに特別と考えられる利益の供与をさします。
被相続人の相続財産を平等に分ける観点から考えると、特別受益があった相続人とない相続人との間で不公平が生じます。そのため、相続人どうしの間で公平性を確保するために、特別受益は遺産の前受け分として考慮され、遺留分算定の基礎に加算されるのです。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
なお、仮に被相続人が遺言で「相続財産に特別受益分を考慮しない(持ち戻し免除)」などの意向を示していたとしても、これは原則として考慮されません。
このような規定があるのにもかかわらず、相続において相続人の間で特別受益がトラブルの原因となりやすい背景は、何をもって特別受益とするかという定義があいまいなためです。たとえば被相続人の子どもに既婚の子どもと未婚の子どもがおり、既婚の相続人の結婚式や新婚旅行、さらには新居費用を被相続人が負担していた場合、未婚の子どもはそれを特別受益と考えるかもしれません。しかし、既婚の子どもはそのように考えない可能性もあるでしょう。
このように特別受益があった・なかったという考え方の違いから、特別受益の有無ひいては遺留分の侵害の有無をめぐって争いの発生があり得るのです。
なお、特別受益として考慮される贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限られるので注意が必要です(民法1044条2項・3項)。
3、遺留分侵害額請求の進め方
では、遺留分侵害額請求は、どのような流れで進めれば良いのでしょうか。確認しておきましょう。
-
(1)当事者間の話し合い
遺留分侵害額請求は、まず遺留分権利者と侵害者の当事者間での話し合いによって解決を図るのが一般的です。遺留分侵害額を請求する意思表示の方法については特段の規定がなく、口頭によるものでも基本的に効力が生じます。
しかし、後日に裁判所での調停や訴訟に至った場合を想定し、遺留分侵害額を請求する際は必ず内容証明郵便を用いましょう。 -
(2)調停
当事者間での話し合いがまとまらない場合、権利者は家庭裁判所に遺留分侵害額の請求をめぐる調停を申し立てることが想定されます。
この調停のことを、「遺留分侵害額の請求調停」と言います。調停は調停委員を介した話し合いです。調停員を介することで当事者間のみよりも、冷静な話し合いが期待できます。
なお、家事事件手続法第257条の規定により、家庭裁判所における遺留分侵害額の請求は調停前置主義を採用しているため、調停を経なければ、訴訟を提起することはできません。 -
(3)訴訟
調停が不調に終わった場合は、続いて遺留分侵害額の請求に関する訴訟に移行することになります。訴訟になると、双方に代理人の弁護士が付くのが一般的です。
遺留分侵害額の請求に関する訴訟は、調停時の家庭裁判所ではなく、被相続人が死亡した時の住所地を管轄している地方裁判所、または遺留分侵害額の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所において行われます。
裁判所による審理の結果、遺留分侵害額請求が認められた場合、遺留分相当額の金銭の支払いが発生することになります。
4、まとめ
遺留分などの遺産分割をめぐり、家族や親族とトラブルになってしまった場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士はトラブルの解決に向けて財産調査やトラブルの相手方である家族や親族との話し合い、さらに調停や訴訟になった場合には、あなたの代理人として弁護活動を行います。
普段からの家族・親族との関係や遺産の額に関係なく、相続におけるトラブルは誰にでも生じ得ることです。
もし遺留分など相続をめぐりトラブルになってしまった場合は、お早めに弁護士へご相談ください。ベリーベスト法律事務所 仙台オフィスでは、相続全般に関するご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|